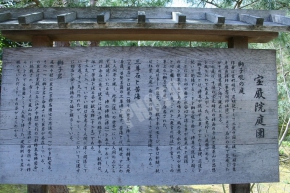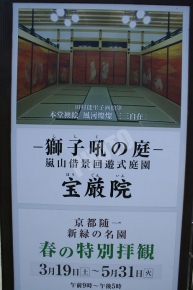| 2011-04-07 |
| テーマ:お寺 | |
| 関連:天龍寺 / 弘源寺 / 宝厳院の紅葉 / 天龍寺の蓮 / 慈済院 / |
宝厳院
 こんにちは京子です。
こんにちは京子です。
本日も、現在特別公開中のお寺をご紹介したいと思います。
 宝厳院(ほうごんいん)です。
宝厳院(ほうごんいん)です。
京都の人気スポットのひとつでもある
嵐山に宝厳院はあります
天龍寺の塔頭(たっちゅう)の宝厳院は
1461年(寛正2年)に室町幕府の管領(かんれい)であった
細川頼之(ほそかわよりゆき)によって創建されました。
ちなみに管領というのは、室町幕府の将軍を
補佐する役職のことです。
細川氏は、斯波(しば)氏、畠山(はたけやま)氏とともに
三管領(さんかんれい)といって
管領になる資格を持つ家だったんですね。
そんな頼之が建てた宝厳院には
広大なお庭がありまして
庭をぐるっと円を描くように
道が補整されていてます。
今回は、道なりにご案内したいと思います
まず、最初に見えるのが無畏庵(むいあん)です。
「無畏」とは、恐れることなく
法を説く事を意味する仏教の言葉なんだそうです。
嵐山に近い事もあって、時代劇の撮影にも
よく使われているそうですよ~♪
こちらで、お茶を頂く事が出来ます。
こちらは、無礙光堂(むげこうどう)です。
別名、永代供養堂とも言います。
 そして、こちらが本堂です。
そして、こちらが本堂です。
2008年に再興されたばかりなので、とても綺麗でした。
本堂内には、ご本尊の十一面観音菩薩が安置されています。
また、現代画家の田村能里子(たむらのりこ)さんによる
障壁画が展示されています
障壁画は「風河燦燦 三三自在(ふうがさんさんさんさんじざい)」
と題された五十八面にも及ぶ襖絵です。
三十三人の老若男女が描かれてるこの作品は
製作期間に一年半もの時間が費やされたそうですよ!
それにしても、この季節ですから境内には・・・
綺麗な桜が咲いています
 みなさんは京都の花見はどちらに行かれましたか??
みなさんは京都の花見はどちらに行かれましたか??
 桜をご覧いただいた後は
桜をご覧いただいた後は
庭園の見所を引き続き、ご紹介したいと思います。
こちらは、「獅子吼の庭(ししくのにわ)」です。
広さは約12,000㎡もあるそうです。
ちょっとしたスーパーのフロアより広い感じですよね。
ちなみに「獅子吼」とは、仏の説法を意味する言葉だそうです。
庭を歩きながら、鳥のさえずりや、風の音を聴く事で
人生の真理を肌を通して感じる事が出来るという
意味が込められているそうです。
獅子吼の庭は、江戸時代の1799年に出版された
京都の名所や名園を案内した本
「都林泉名勝図会(みやこりんせんみょうしょうずえ)」に
掲載されていて、昔から有名な名所だったようです。
獅子岩(ししいわ) です。
です。
その名の通り獅子の姿をした巨大な岩です。
右側が頭ですよ~♪
こちらは豊丸垣(ほうがんがき)です。
竹で出来た垣根ですね。豊丸とは茶人の名前だそうです。
 庭を流れる小川の向こうに見えるのは本堂と無礙光堂です。
庭を流れる小川の向こうに見えるのは本堂と無礙光堂です。
そして椿も咲いていました。
こちらは福鼓(ふくつづみ)と呼ばれる椿なんですね♪
嵐山には渡月橋と呼ばれる橋があります。
その橋の下を流れているのが大堰川(桂川)です。
これはその橋に
以前、取り付けられていたものなんですね。
 それにしても桜が綺麗ですね~♪
それにしても桜が綺麗ですね~♪
こちらは、青嶂軒(せいしょうけん)です。
大正時代に作られた建物を修復して
新しく2003年に作られたものです。
最後にご紹介するのは、宝厳院垣(ほうごんいんがき)です。
数十メートルに渡って張り巡らされていましたよ。
と、いう事で今回は春の特別公開中の
宝厳院をご紹介しました。宝厳院の場所はコチラ↓
最寄の交通案内
 京福電車(嵐電) 嵐山本線 嵐山駅(あらしやまえき)
京福電車(嵐電) 嵐山本線 嵐山駅(あらしやまえき)雑談掲示板 新着