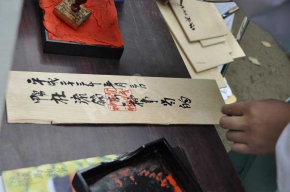| 2013-08-30 |
| テーマ:その他 | |
小笠原流の弓馬術礼法が楽しめる祭一覧
今回ご紹介するのは・・・
小笠原流(おがさわらりゅう)の
弓馬術礼法(きゅうばじゅつれいほう)が楽しめる祭一覧です!
ピーン!とこない方もいらっしゃると思いますが
下鴨神社で流鏑馬(やぶさめ)やっている方々!
・・・と、言えばお分かりですよねっ
彼らは、小笠原流と言われる鎌倉時代から続く
弓術・弓馬術・礼法の流派で、古来より
源氏を始め、足利家、徳川家の弓術指南役を行ってきました。
※ちなみに『弓馬術礼法』は弓術・弓馬術・礼法の総称です。
こうした事もあり、神社の祭(弓矢を使った奉納行事)において
活躍されているというワケです!
※全国的に活動されていて、伊勢神宮や熱田神宮、鶴岡八幡宮でも弓馬術礼法が奉納されています。
今回はそんな中から、弓馬術礼法が行われる
京都の祭(神事)をご紹介したいと思います!!
武射神事は、厄除けを目的とした神事で
『鬼』と書かれた的を矢で射抜き1年間の除災を祈願します
ちなに、この武射とは『地上で弓を引く事』を指し
小笠原流の武射神事では
鎌倉時代に考案された5つ程の作法の中から
『蟇目(ひきめ)の儀』『大的式(おおまとしき)』『百手式(ももてしき)』
と呼ばれる3つの作法が披露されるんですよ。
ただ矢を放つというだけでなく
着物の紐をほどく所作や、弓矢の取り回し方まで
細かく決められた動作も見所の1つです
横一列になった射手が、動きを綺麗に合わせながら
弓を引く瞬間は大変美しく、流鏑馬(馬に乗って矢を射る作法)とは
また違う魅力を感じる事が出来ます。
※詳しくは歩射神事 2013(下鴨神社)の記事をご覧下さい。
こちらは弓ではなく小笠原流の『礼法』に基づき
新成人達が、直垂(ひたたれ)や水干(すいかん)に着替え
冠(烏帽子)を頂き、大人の仲間入りをする儀式で
小笠原流の方々が介添人として参加されます!
※元服(げんぷく)とは成人儀礼の1つです。時代により多少前後しますが、武家の場合であれば、男の子は10代半ばで元服するんですよ。
こちらも弓と同じで、ただ服を着るだけではなく
小笠原流が代々受け継いできた礼法が詰め込まれているんですね。
着物を着る順番や、袖を通す順番など細やかな作法がある他
その後いただく食事(宴会)まで
小笠原流の『礼法』に基づき行われます。
5月-流鏑馬神事(下鴨神社)
紫式部の書いた『源氏物語』にも登場する
流鏑馬神事は、現在も人気の神事の1つで
当日は開始の6時間前から
観覧者による長蛇の列が出来る程なんですね~
小笠原流による流鏑馬神事は
具体的にどういった内容かと言いますと・・
境内の『糺の森』に設けられた
全長約400メートルの馬場の上を、騎乗して駆け抜けながら
3つの的を次々と射るというものです
見事に射抜いた瞬間は、会場は割れんばかりの
拍手で会場は一つになります。
ちなみに、割れた的は『縁起物』という事から
毎年あっという間に無くなるんですよっ。
※詳しくは流鏑馬神事 2011(下鴨神社)の記事をご覧下さい。
5月-歩射神事(下鴨神社)
葵祭にさきがけて行われる神事で
祭の当日、斎王代を中心とした行列が歩く参道を
弓矢で清め、安全を祈願するというものです。
神事は『屋越式(やごししき)』に始まり
その後、10人の射手が10手を射る『百々手式』が行われます。
※詳しくは、歩射神事 2013(下鴨神社)の記事をご覧下さい。
葵祭では、御所を出発した行列が
下鴨神社・上賀茂神社と巡行し、それぞれで社頭の儀を行いますが
この日、小笠原流の方々は
行列が下鴨神社に到着した際に、糺の森の馬場において
『走馬の儀』を執り行います。
一頭ずつ馬を走らせ、馬上にて鞭(むち)を振ります
鞭の振り方にも、細やかな所作があるようですよ!
※上賀茂神社でも『走馬の儀』は行われますが、こちらは小笠原流の方々では無いそうです。
9月-萩まつり(梨木神社)
梨木神社では毎年9月に
3日間かけて『萩まつり』が行われます。
期間中、さまざまな奉納行事がありますが
その一環として小笠原流による
『三三九手挟式(さんざんくたばさみしき)』が行われます。
元々は、武家において正月4日の『弓始め』に行われていた儀式で
射手が2人ずつ並び
交互に、的に向かって打ち合うものです
的の裏側には『邪魔退散』と小さく書かれているそうで
これを射抜く事で
天下泰平を祈願していたという事ですよ~っ!
※三三九手挟式について、詳しくは萩まつり 2012 その1(梨木神社)の記事をご覧下さい。
10月-袴着の祝・帯直しの祝(梨木神社)
これは七五三の祝いとして、行われるもので
小笠原流の礼法のもと、5歳の男の子には袴を着せ
7歳の女の子には帯を結ぶもので
小笠原流の方々は
男児の着付けの介添役として参加されています。
それぞれを
『袴着の祝(ちゃっこのいわい)』『帯直しの祝』と呼び
子供たちの晴れ姿を祝います。
という事で、今回は小笠原流の弓馬術礼法が
楽しめる祭(神事)をご紹介させていただきましたっ
この他にも、2012年に限りですが
小笠原流による三々九手挟式が奉納されました
※詳しくは伴緒社祭 2012(白峯神宮・伴緒社)の記事をご覧下さい。
それぞれの神社の場所はコチラ↓
より大きな地図で 小笠原流の弓馬術礼法が楽しめる祭一覧 を表示 Tweet
雑談掲示板 新着