今回ご紹介するのは
京都府木津川市(きづがわし)にある

相楽神社(さがなかじんじゃ)です!
相楽神社の読み方は
相楽と書いて『さがなか』と読むんですよ

どうして『さがなか』と読むのかについては
悲しいエピソードが残っているんですけれど
それはまた後で、お話するとしまして
まずは神社について
簡単ではありますけれどご紹介しますね♪
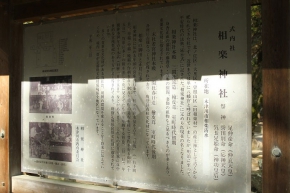
相楽神社の創建は
実は詳しくはわかっていないんですけれど
旧・相楽村(北ノ庄、大里、曽根山)の
産土神(うぶすながみ)として
篤く崇敬されてきたみたいです
そんな相楽神社なんですけれど
もともとは八幡宮(はちまんぐう)と
呼ばれていたみたいなんですね~

これは神社のご祭神が
・誉田別命(ほんだわけのみこと:応神天皇(おうじんてんのう))
・神足仲彦命(かんたらしなかひこのみこと:仲哀天皇(ちゅうあいてんのう))
・気長足姫命(おきながたらしひめのみこと:神功皇后(じんぐうこうごう))
という八幡神が祀られている為だといわれています
※誉田別命、神足仲彦命、気長足姫命の3柱を総称して八幡神というんですね。八幡神につきましては、京の八幡宮巡りの記事をごください。
その後、1877年(明治10年)に
『延喜式(えんぎしき)』神名帳に
『相楽(サカラカノ)神社』と
書かれている事がわかって
相楽神社と呼ぶようになったというワケです
※延喜式(約50巻)とは、平安時代に藤原時平(ふじわらのときひら)らが中心となって作った(律令の)施行細則です。神名帳とは全国の神社一覧が記載された延喜式の第9、10巻にあたります。
それでは中に入っていきましょう♪
鳥居をくぐって左手側に
手水舎(てみずや、ちょうずや)があります。

こちらの手水舎の手洗石は
1793年(寛政5年)に雨乞いの祈願の為
氏子の方が寄進したものなんだそうです
こちらは表門です!

表門にはかつて『八幡宮』と
呼ばれていた名残からなのか
八幡宮と書かれた額がかけられていましたよ♪
その表門をくぐると
左右に宮座の方達が集まった際に使用される
南仮舎(みなみかりや)と北仮舎(きたかりや)があります。

 南仮舎
南仮舎

 北仮舎
北仮舎
10月17日の秋祭の際には
九座九十人の十人衆が紋付羽織で
当屋から有職料理の餐応(きょうおう・おもてなし)を
受けるそうです
※当屋は当座とも呼ばれていて当番制で回ってくる祭の当直の家の事です。10年くらいの間隔で当たるみたいです。
そして正面には拝殿がありました。

こちらは拝殿の左後ろにある豊八稲荷大明神です。

お稲荷さんですよね。
そのお稲荷さんの前には、なんと!
宝船が置かれていましたよ~♪

そしてこちらが本殿になります。

本殿には冒頭で触れました
八幡神がお祀りされています
また、本殿の周りには
末社として5社(左から松枝神社、鳥懸神社、若宮神社、小守神社、清水神社)があります。
さて、冒頭でも触れました
相楽をどうして『さがなか』と
読むのかと言いますと・・・
これは古事記を読めばわかります
古事記の垂仁段によりますと
丹波出身の4人の姉妹が
垂仁天皇(すいにんてんのう:第11代天皇)に
同時に嫁いだそうです
え?4人?と思うかもしれませんけれど
そこは気にしちゃダメです
昔は一夫多妻制が普通にあったんですよね。
けれどその4人のうちの2人は
あんまり美人さんじゃなかった・・・
いえ、もう少しハッキリと言いましょう!
いわゆる不細工だったみたいなんです
それで垂仁天皇は
不細工だった2人を里に
送り返してしまいます
あれ?どっかで聞いた話のような気が・・・
木花咲耶姫命(このはなのさくやひめのみこと・木花開耶姫命)と
磐長姫命(いわながひめのみこと)の話も
こんな感じでしたよね??
※詳しくは、大将軍神社(西賀茂)の記事をご覧下さい。
少し話が逸れてしまいましたけれど
返されてしまった2人の内の1人である
円野比売命(まとのひめのみこと)は
あまりにもショックな出来事だったようで
里に戻る途中、山城国の相楽に入った時に
「同じ姉妹の中で醜いという理由で返された事は、きっと近所で噂になる・・・なんと恥ずかしい事なのでしょう」
と言ってなんと
木の枝に取り懸がって(さがって)
自殺を試みるんですね
皆さんの中には
もう気づいてしまった方も
いるのではないでしょうか。
そうです!それ以降、その場所の事を
『懸木(さがりき)』と呼び
これが後に訛って・・・
『さがなか』となったんだそうですよ
こちらは相楽神社の南に

今でもある懸木社(さがりきしゃ)です!
相楽を『さがなか』と読む理由は
こういった事があったからなんですね~。
それにしてもその後
円野比売命がどうなったのか気になりますよね
円野比売命は
ある場所で深い淵に落ちて
死んでしまったといわれています
ちなみにそのある場所は
その後、堕国(おちくに)と
呼ばれるようになったそうで
現在は『乙訓(おとくに)』という
地名になっています。
※乙訓は、京都市の南西にある地名です。
そんな相楽神社の場所はコチラ↓











