こんにちは京子です!
今回ご紹介するのは
2月17日に粟田神社で行われた・・・
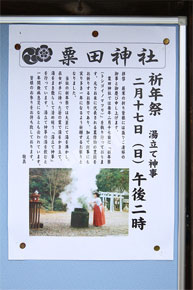
祈年祭(きねんさい・としごいのまつり)です
宮中行事でもある祈年祭は
五穀豊穣を祈願する神事です。
これに加え、粟田神社では
「何事にも実り多き1年となりますように。」という
願いを込めて行われます

祈年祭では、祝詞の奏上に加え
巫女による神楽や湯立て神事も行われるんですよ~

粟田神社は
かつて京の七口の1つであった『粟田口』に建つ神社です。
京都の出入り口となっていた為
粟田神社に旅の安全を祈願をする人々が多かったそうですね。
こうした事から『交通安全のご利益がある神社』として
知られています。
※幕末には、京都から江戸へと降嫁した皇女『和宮(かずのみや)』の御降嫁(ごこうか)行列も祈願されたそうです。
では早速レポートしたいと思います

14時より神事が始まると
まずは巫女や参列者、そして
今回の『湯立て神事』で使う大きな釜に
お祓いを行います。
その後、本殿の御扉(みとびら・本殿の扉)を開けて
祝詞(のりと)を奏上します。

この後、舞殿にて
巫女による神楽が奉納されますっ
舞は『式神楽(しきかぐら)』と呼ばれるものです。
鈴を右手に持ち、両手を高く上げながら
定位置で何度もくるくると回るシンプルな舞です。

 釜は文政時代のもので、今から200年ほど前との事ですよ。
釜は文政時代のもので、今から200年ほど前との事ですよ。
続いて、釜の前でも同様に
巫女が神楽を舞います。
今度は、早神楽(はやかぐら)と呼ばれる舞で
先ほどの式神楽と動きは似ていますが
回るスピードが速いという点が特徴的でしたね~。
神楽が終了すると
・・いよいよ湯立て神事が始まります
笹を使って湯を振り撒き、お祓いを行います。
ちなみに、このお湯を浴びれば
無病息災で過ごせると言われているんですよね。
まずは、沸騰した釜の湯の中に
塩、米、酒を入れて御幣でかき混ぜます。

 米を釜に入れています。
米を釜に入れています。

 こちらはお酒ですね~。
こちらはお酒ですね~。
祓い清める為のお湯が完成すると
一部を汲み取って、神前に供えます。

以上の作法が終わると
笹を使って、お湯を一面に振り撒きます
宮司や参列者が見守る中
巫女は両手の笹を、釜の湯にじっくり浸した後
辺り一面に、何度も
お湯を振り撒きますっ。
近くで見ていた方々にも
しっかりと、しぶきが届いたのでは無いでしょうか?
そして最後に
湯立て神事のお下がりである
『釜の湯』が参拝者に振舞われていましたよ
こうして15時前に、全ての神事は終了しました。











