こんにちは京子です
さて、本日は少し変わったものを取り上げたいと思います~っ。
いつもよく取り上げている
神社でもなく
お寺でもなく
カフェでもなく
(・∀・)ノ古墳ですっ。
その名も・・・

蛇塚古墳(へびづかこふん)
 さて、この蛇塚古墳があるのが、京都の太秦という地域。
さて、この蛇塚古墳があるのが、京都の太秦という地域。
この蛇塚古墳は
太秦という地域と深く関わりがあるんですね
 本日はそのあたりを詳しくご紹介したいと思います!
本日はそのあたりを詳しくご紹介したいと思います!
さて、この蛇塚古墳は
全長約75メートルあったと予測されていて
現在は、古墳の石室部分だけが残っています。
※石室というのは石積みの墓室の事を言います。
と言っても、この石室部分だけでも
 なななんと!全長17.8メートルもあり
なななんと!全長17.8メートルもあり
面積で比較すると、日本で第4位という石室の大きさなんですね
ちなみに蛇塚古墳周辺は住宅街ですから
家々に囲まれた状態で
全長17.8メートルの石室が
どどーーん!とあるワケですから
なかなか異様な光景だとも言えちゃいます
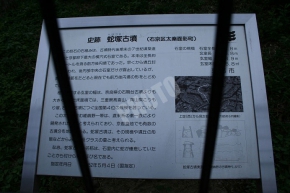
さて
まず「古墳」について、以前にも宇治上神社で
説明させていただいていますが
軽くおさらいをしますと
みなさんご存知だと思いますけれど・・・
(・∀・)ノ古墳ってのはお墓です
あ・・
 そりゃ知ってますよね(汗)
そりゃ知ってますよね(汗)
古墳が大量に作られたのは3世紀から7世紀。
 しかーし、古墳とひと言で言っても
しかーし、古墳とひと言で言っても
その時代に応じて作り方や
埋葬されている人や、副葬、つまり埋葬品が変わっているんですね。
 ではどのように移り変わっていったのかと言いますと
ではどのように移り変わっていったのかと言いますと
まずは初期の古墳!
竪穴式といって
上から穴を掘って埋葬して埋めるというパターンだったのです。
これは後に登場する、横穴式とは違い「追葬」が出来ないんですね。
追葬とは・・・古墳を作った後、一人を埋葬し、その古墳に次の人を入れて、またその次の人を入れてとどんどん追加していく事なんですね。
その追葬が出来ない仕組みとなっているのが、この竪穴式と言われる初期の古墳です。
つまり、もう一人埋葬しようとすると再び穴を掘り返さなくてはいけなくなるからですね(汗)
ちなみに
どんな人が埋葬されていたかというのは
一緒に埋葬される道具
(副葬と言って死者が生前利用していた物を一緒に入れます)
から予測されるんですね
この初期の古墳は
銅鏡や碧玉(へきぎょく・微細な石英の結晶が集まってできた鉱物)製の装身具が一緒に埋葬されていていて、これらの物は
呪術的であり、宝器的な要素を含んでいたと考えられています

 この蛇塚古墳は崩落の危険性があるという事で柵がしてあります
この蛇塚古墳は崩落の危険性があるという事で柵がしてあります
では、それとは対照的に
中期になるとどうなるの
 と言いますと
と言いますと
武器や武具、馬具が副葬されています
つまり、武力を持つ権力者や地方の有力な豪族が
埋葬されていたという事がわかりますね。
ちなみに後期の古墳では
農具である、鎌や鋤(すき)などが副葬され
徐々に埋葬される人物の対象が広がっていったのです
簡単にいうと、とっても偉い人だけが埋葬されていた時代から徐々に、有力農民も埋葬されていくようになったというワケです
※初期古墳の特徴だった竪穴式は埋葬される人間はひとつの古墳につき一人でした。けれども中期・後期になるにつれて竪穴式から横穴式へと変わり、ひとつの古墳に何人も埋葬される追葬が可能になった事からもわかります。
そしてこちらの蛇塚古墳は、
横穴 竪穴
竪穴 どっち
どっち

・・と言いますと

横穴式 なのです。
なのです。
横穴式には玄室(げんしつ)という棺を納める部屋があり
玄室と外部とを結ぶ通路部分を羨道(せんどう)と言います。
この写真に写っているのはその羨道部分なのですね
ちなみに
この蛇塚古墳の名前がついた由来は
石室内に蛇が棲息し、岩石の間から出入りしていた事から名付けられたそうですよ
では、次に・・・
蛇塚古墳にはどんな人が埋葬されていたの と言いますと
と言いますと
この蛇塚古墳のある場所は京都の太秦(うずまさ)です・・・
そうです
これでピンと来る人もいらっしゃると思いますけれど
秦氏ですね
この蛇塚古墳には秦氏が埋葬されていたと言われています。
※秦氏は渡来系民族で、弓月君(ゆづきのきみ)という人が朝鮮半島の百済から18670人を率いてやって来た民族だと言われています。
他にも新羅からやって来たという説もあります。
こうした背景には、高句麗が朝鮮半島を南下し始め、新羅は高句麗の影響下に置かれ、それに押されるように日本に渡来してきたというワケです

 この古墳を囲む家々は「玄関あけたら目の前に古墳」って状態なんですから、なかなか刺激的ですよね~(笑)
この古墳を囲む家々は「玄関あけたら目の前に古墳」って状態なんですから、なかなか刺激的ですよね~(笑)
ちなみに、太秦は古墳だけでなく
広隆寺は聖徳太子から仏像を授かった秦氏が、蜂岡寺(広隆寺の古称)を造った事で有名で、こちらは秦氏の氏寺です。
また、製陶、養蚕、機織などの技術に優れていた秦氏は
織物の祖神を祀った「蚕養神社」がある事から名前のついた神社「木嶋神社(蚕の社)」もあります。
太秦という地名の由来も
機織である絹を「うず高く積んだ」事からついたという説や
秦氏の拠点を「太い」という字で表し太秦と読んだと言われています。
つまり、
太秦=秦氏
と裏付けられるのです
 秦氏は技術面は非常に高く、その他にも
秦氏は技術面は非常に高く、その他にも
嵐山にある大堰川(おおいがわ)などの治水事業も行っていたんですね。
京都に流れる川の氾濫を抑え
荒れ果てた地を整備し平安京を作る為に
多大なる貢献をしたと言われています。
 それほど、京都で秦氏というのは力を持っていて有力な人材が数多くいたんですね。
それほど、京都で秦氏というのは力を持っていて有力な人材が数多くいたんですね。
ちなみに、
京都御所にある紫宸殿は
秦河勝(はたのかわかつ)の居宅跡に桓武天皇が建てたとさえ言われてるんですね~
そんな秦氏が埋葬されている蛇塚古墳の場所はコチラ↓
大きな地図で見る










