こんにちは京子です
さて、昨日の萬福寺に引き続き京都宇治にある神社仏閣の一つであり
本殿は世界遺産にも登録されている・・・

宇治上神社(うじがみじんじゃ)です
 ではでは行ってみましょう~
ではでは行ってみましょう~

この京都宇治の辺りは、幾つもの神社仏閣が集合していまして
大小合わせて20以上
京子ブログでも現在までに

京都宇治は、一度に多くの神社やお寺を回れる観光コースとしても有名なのでこの辺り一帯は観光客で溢れているんです
 この宇治上神社は宇治川を挟んで、向かいに平等院があるので両方回られている方も多いのでしょう!
この宇治上神社は宇治川を挟んで、向かいに平等院があるので両方回られている方も多いのでしょう!
しっかりと各神社などの道案内がありとても行きやすいです
その平等院とほぼ同じ時代に作られ
元々は同じく、近くにあります宇治神社とニ社一体だったそうで
 宇治上神社を離宮上社、または本宮
宇治上神社を離宮上社、または本宮
 宇治神社を若宮または離宮下社、または若宮
宇治神社を若宮または離宮下社、または若宮
と呼び、両方を合わせて宇治離宮明神、または八幡宮と呼ばれていたそうです
それが明治になり分社したのですね
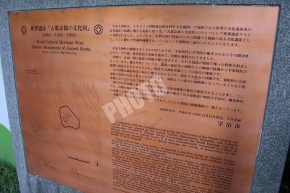

まず、大きな鳥居をくぐり門を入ります。
その奥に見えるのは・・・・

二つのお山を発見
こちらは清め砂ですね~っ。
 じつはこの砂、盛ってあるだけでなく
じつはこの砂、盛ってあるだけでなく
購入も可能なのです。
ちなみにこの清め砂の使い方ってご存知ですか??
どういった効果があるかというと・・土地の神様を沈める為なのです。よく、家を建てる時に使ったり、家の災いを鎮める効力があるそうでこの砂を家の周囲に撒くんですね。
さて、
その清め砂の向こう側にあるのが・・・

拝殿です。
これらが作られたのは鎌倉時代
何より、これほど長い期間、潰れずに残っているという事は
技術の高さの表れとも言えるんではないでしょ~か

そして、右手を見てみると
なんだかある場所に人が引き込まれていってます・・・
 ん~?
ん~?
これ何だろうというと・・・

桐原水(きりはらすい)
宇治七名水のひとつとして残っているこちらの桐原水。
地元の方などが汲みに来ているのか杓子などが置いてありましたよ。
※ちなみに飲み水には適していないそうですのでご注意くださーい!
そして、その桐原水から
階段を昇っていくと次に見えてくるのが

どどーーーん!
世界遺産に登録されている本殿。
それもそのはず調べによると1060年に建てられた
現存する神社建築の中では
日本最古なのです

 本殿の屋根は流造(ながれつくり)と言うそうです。特徴的ですね~っ。
本殿の屋根は流造(ながれつくり)と言うそうです。特徴的ですね~っ。
じつはこの本殿、
じーーーっと中を覗くと
 中には三つの内殿が作られておりそれを覆い囲うように作られているんです。
中には三つの内殿が作られておりそれを覆い囲うように作られているんです。
その3つの内殿に祀られているのが
仁徳天皇(にんとくてんのう)
応神天皇(おうじんてんのう)
菟道稚郎子皇子(うじのわきいらつこおうじ)
の3人です。
さて、仁徳天皇と聞いて今回お話したいのが・・・
古墳のお話っ
そうです!
世界で一番巨大なお墓って誰のお墓かご存知ですか?
クフ王のピラミッドじゃないんですよ
なんと、この仁徳天皇のお墓である
大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)なんです。
全長486メートルのビッグなお墓。この大仙陵古墳は前方後円墳であり、カギ穴の形の古墳と言えば皆さんピーンときますよね
ちなみに前方後円墳とは読んで字の如く!
向きは間違いやすいかもしれないですけど
あの鍵穴の丸の部分が後ろ向き、台形の部分が前になります
そんな古墳が大量に作られたのが
 3世紀後半から7世紀前半にかけて。
3世紀後半から7世紀前半にかけて。
お墓と言えば
それまでは石を組み上げただけの支石墓(しせきぼ)が一般的でした。
それが権力の象徴として古墳が作られるようになりました。
「俺が死んでも、俺ってヤツがいかに凄かったを伝えたい!」
という目的で作られたのが古墳の始まりです。

 こちらは天降石。置いた石が落ちなければ、願いが成就すると言われています。
こちらは天降石。置いた石が落ちなければ、願いが成就すると言われています。
古墳が作られた場所(大阪や奈良が多い)や
大きさ、そして古墳から一緒に出土される物
・・・例えば、ある時は武器!ある時は農具!などなど
その時代背景がとても反映されているのですね~。
しかーし、その古墳を作るオンパレードは
ピタリと止まるのです。
その理由とは・・・
(・∀・)ノ538年の仏教公伝がきっかけとなります
 645年~646年に起こった政変である「大化の改新」の中で
645年~646年に起こった政変である「大化の改新」の中で
古墳にかける労力・経済力の負担を減らす為に
薄葬令(はくそうれい)が出され
これにより、墓の大きさや規模が制限されたのですね。
そして、この仏教の伝来により墓を大きくする代わりに
有力な豪族たちは
 大きな寺院を作る事で権力の大きさを表すようになりました。
大きな寺院を作る事で権力の大きさを表すようになりました。
そうですよね・・・
あれだけ大きな古墳を毎度毎度
作ってたら
もう・・・古墳を作る場所が
日本には無くなって
も・・・
もしかすると・・・
今頃は・・・
( ´Д`)超高層古墳や、地下古墳帝国なんて登場してたかも知れませんね。
考えただけで恐ろしい・・・(汗)
そんな宇治上神社の場所はコチラ↓
大きな地図で見る











